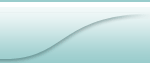|
|
|
私たちの周辺には、色々な音に囲まれています。
イライラするなどの心理的影響や頭痛、血圧上昇などの生理的影響を人体に与えます。
このように、人に様々な影響を与える 音 とは、どのようにして人に影響を与えるのでしょうか?
音には、3つの要素(強弱、高低、音色)があります。
騒音を計る際に目安になる、音の強弱(db、デジベル)と音の高低(Hz、ヘルツ)について説明させて頂きます。
|
電車が通る橋の下や、ささやき声、車のクラクション…
様々な音が私たちを取り囲んでいますが、これらの音の力そのものを数値化して、
どれだけ大きな音か ということを表した数値をデジベル(db)と言います。
通常の日常会話は、約60デジベル(db)と表現されます。
下記に具体的な状況におけるデジベル値を示します。
| 120デジベル | 飛行機のエンジン近く、ビル工事現場 |
| 110デジベル | 自動車のクラクション(前方2m) |
| 100デジベル | 電車の通るときのガード下 |
| 90デジベル | 騒々しい工場内、大声による独唱 |
| 80デジベル | 地下鉄の車内、TVの大音量 |
| 70デジベル | 電話のベル、騒々しい事務所 |
| 60デジベル | 普通の会話、静かな自動車の中 |
| 50デジベル | 一般の住宅地 |
| 40デジベル | 深夜の住宅地、図書館 |
| 30デジベル | ささやき声 |
| 20デジベル | 木の葉のふれあう音 |
音は空気を振動させることにより発生し、その振動を私たちの鼓膜でとらえることにより音として感じることができます。
その振動の大きさだけを比較することにより、音の質ではなく音の力そのものを計るのがデジベルという単位になります。
この大きさが、騒音を比較する際の目安にはなります。
しかしながら、われわれの耳は、音の 高い 低い によって 聞こえやすかったり、聞こえにくかったり するので、この単位だけで 比較することは、難しいです。
|
音は空気を振動させることにより発生し、その振動を私たちの鼓膜でとらえることにより音として感じることができます。
その際、空気を振動させる回数が多い音のことを、「高い音」と表現し、逆に、振動させる回数が少ないものを 「低い音」と表現します。
この振動数、通常一秒間に何回振動しているかということを表す(ヘルツ)ことにより、他の音と比較します。
この数値(Hz , ヘルツ)が大きいほど、高い音となり、この数値が小さいと、低い音になります。
人間の耳で聞き取れる範囲は、20Hz〜20,000Hzと言われています。
話す言語によっても変わってきますが、日本語の場合、普段の会話の周波数は125〜1500ヘルツ前後と言われています。
|
Noise Reduction Rating (ノイズ減少率)の略で、決められた低い音から高い音(周波数 Hz)の遮音性能(遮音性能 デジベル)を計測し、
そのデータを元にした、どれだけの遮音性能があるかを簡単にわかるようにした目安です。
NRRが30の場合、普通の日常会話(60デジベル)が、ささやき声(30デジベル)程度になるであろうという基準になります。
つまり
60デシベル(日常会話)− 30デシベル(装着する耳栓、イヤーマフのNRR値)
=30デシベル
NRR30とは、日常会話程度の騒音の場所でつけた場合、聞こえる音は、ささやき声程度になるであろうと期待される 遮音器具 ということになります。
|
|
|